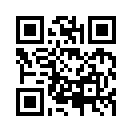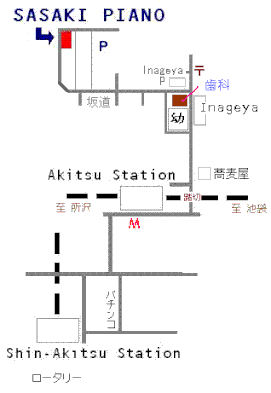古いピアノを修理していると、現代のピアノとはアクションの機構の違いや、その他のパーツの収まりに当時のピアノ職人さんの創意工夫が見られ、現在のピアノに至るまでの系譜の片鱗を感じられます。
こちらのピアノ
スタインウェイのアンティークで型番不明。
響板貼替えのため鋳鉄製のフレームを外そうとしたところ、
フレームが上下に分かれている、現代ではお目にかかれない構造。
上側の金色の部分は、ネジをはずして簡単に取れたが、
下側の黒の部分のネジをすべて外してもフレームが外れない…
試行錯誤の結果、どうやらフレームの上側をクサビ状にしてピン板かませて、膠を流しこんで高さを調整しつつ固定、さらにフレームに対して斜めにネジを固定する事で、クサビ状の部分が外れないようにしてある。
外すのも手間だが、固定するのも手間のかかる構造だ。
そして、言葉では説明出来ている気がまったくしないので、図が必要だと思わせる構造だ。
すいません。今度手書きの図を用意しておきます。
語彙力については、言わないであげて下さい。
作業の進行具合はちょくちょくこちらでご紹介していきます。
有限会社ササキピアノ